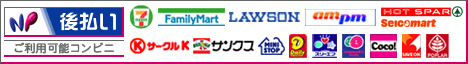南インドのアーンドラ・プラデーシュ州に位置するシュリーカーラハスティ寺院は、シヴァ神を祀る由緒ある寺院として知られています。
この寺院は、パンチャ・ブータ・スタラ(五大元素を祀る寺院)の一つとして、「風(ヴァーユ)」の元素を象徴する重要な巡礼地となっています。
伝説によれば、風の神であるヴァーユは、ここで数千年にわたりカンファー(樟脳)でできたシヴァリンガムに対して苦行を行いました。
すると、苦行に喜んだシヴァ神が現れ、ヴァーユに三つの恩恵を授けます。
一つは、世界中に空気として存在すること、二つ目は万物の中にヴァーユ(風の要素)として存在すること、三つ目は崇拝したリンガムが「ヴァーユ・リンガム」として知られ、多くの者に崇拝されることでした。
こうしてこの地は、「風」の元素を象徴する重要な聖地となります。
また、寺院の名称の由来となった興味深い神話も伝わります。
かつて、蜘蛛(スリ)、蛇(カーラ)、象(ハスティ)の三者がこの地でシヴァ神を深く信仰し、解脱を得たという神話です。
寺院に住まう蜘蛛は、巣を張りながら精巧な神殿やシヴァ神の像を織ってシヴァ神を崇拝していました。
ある日、風が吹いて、祭壇のランプの火がこの蜘蛛の供物を燃やしてしまいます。
蜘蛛は自らの命を危険にさらして、火を飲み込もうとしました。
この献身に胸を打たれたシヴァ神は、蜘蛛に解脱を与えます。
蛇は、自らが守る貴重な宝石をシヴァリンガに捧げ、日々礼拝していました。
ある日、蛇が礼拝を終えると、近くの川で清めの沐浴をしたばかりの象がやってきて礼拝を始めます。
象は鼻からシヴァリンガに水を注いで礼拝するも、その勢いで蛇の捧げた宝石が散らばってしまいました。
戻ってきた蛇は、自分の捧げ物が台無しにされたと感じ、再び宝石を捧げます。
このやり取りが毎日続くうちに、蛇は怒りを募らせ、自分の捧げ物を台無しにする者を罰することを決意しました。
そして、象が礼拝に訪れた時、蛇はその鼻を這い上がり、毒を注ぎ込みます。
苦しむ象は暴れ、蛇を押しつぶし、結果として両者とも命を落としてしまいます。
しかし、シヴァ神への深い献身と、命をかけた信仰を認めたシヴァ神は、両者に解脱を授けます。
この神話は、寺院の名前であるシュリーカーラハスティの由来を説明するだけでなく、その形や種に関係なく、誰もが解脱を得ることできるということを伝えています。
また、狩人のカンナッパが自身の目をシヴァ神に捧げた献身の物語や、パールヴァティー女神が人間の姿となった呪いを解かれた物語など、数々の伝説が伝わり、この寺院の神聖さを物語っています。
寺院の歴史は古く、内部の聖堂は5世紀のパッラヴァ朝にまで遡るとされます。
また、11世紀頃に本殿や壮麗な塔門(ゴープラム)が、16世紀頃には120メートルの主塔門や100本の柱を持つ柱廊が建立され、現在の荘厳な姿が完成したとされます。
その建築様式は南インドのドラヴィダ様式を代表するもので、精緻な彫刻で装飾された塔門や柱廊が特徴的です。
主祭壇には象の鼻のような形をした白い石のシヴァリンガ(ヴァーユ・リンガ)が安置されています。
シュリーカーラハスティ寺院で祀られるヴァーユ・リンガは生命の呼吸を示し、ここでの祈りは罪や病気の浄化を象徴するとされます。
また、シュリーカーラハスティ寺院はインド占星術におけるラーフとケートゥに関連する寺院としても重要視されています。
他の寺院の多くが閉門する日蝕・月蝕の際も開門し続け、これらの惑星による悪影響を和らげる特別な儀式が執り行われます。
この地は「南のカイラーサ」とも称され、シヴァ神への深い信仰の中心地として、多くの巡礼者が訪れます。
毎年、マハーシヴァラートリなどの祭典が盛大に執り行われます。
このように、シュリーカーラハスティ寺院は、豊かな神話と歴史、荘厳な建築、そして深い信仰が織りなす南インドの重要な文化遺産として、今日も多くの巡礼者や訪問者を魅了し続けています。