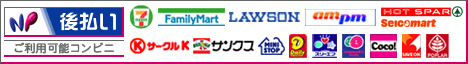ジェーシュタ・ガウリー・アーヴァーハナ
ジェーシュタ・ガウリー・アーヴァーハナについて

インド西部マハーラーシュトラ州を中心に行われるジェーシュタ・ガウリー・アーヴァーハナは、家庭の繁栄と幸福を祈ると同時に、宇宙の根源的な女性エネルギーであるシャクティを讃える三日間の祭礼です。
ガネーシャ神の降誕を祝うガネーシャ・チャトゥルティーの期間中に行われ、暦では、バードラパダ月(8月〜9月)のシュクラ・パクシャ(新月から満月へ向かう半月)の八日目(アシュタミー)からの三日間にあたります。
祭礼は、初日に女神を招くアーヴァーハナ、二日目に礼拝のプージャー、三日目に送り出すヴィサルジャナという流れで進みます。
家庭に神聖な力を迎え、心を尽くしてもてなし、再び宇宙へと還すことで、人と神、家庭と宇宙の結びつきを深く体験するものとなっています。
この祭礼を理解するには、祀られる二柱の女神、ガウリー女神とジェーシュター女神の物語を知る必要があります。
ガウリー女神は「黄金に輝くもの」を意味し、シヴァ神の妃パールヴァティー女神の別名です。
彼女はかつてダクシャ王の娘サティーとして生まれましたが、父に夫のシヴァ神を侮辱されて命を絶ち、その後ヒマーラヤ王の娘パールヴァティー女神として転生しました。
厳しい苦行の末に再びシヴァ神と結ばれたことから、ガウリー女神は貞節と再生の象徴とされ、家庭に迎えることで浄化と繁栄をもたらすと信じられています。
一方で、ジェーシュター女神はラクシュミー女神の姉とされ、妹が富や吉祥を象徴するのに対し、不運や貧困と結びつけられてきました。
乳海攪拌の神話において、猛毒の後に現れたとされるため、不吉な存在と恐れられます。
しかし、この祭礼では、ジェーシュター女神は単なる忌避の対象ではなく、豊穣をもたらすために必要な対極と考えられます。
ガウリー女神やラクシュミー女神とともに祀ることで、幸福と不幸、豊穣と欠乏は切り離せない一体の力だと示され、不吉を受け入れることでこそ真の繁栄が得られるという智慧が表されています。
三日間の儀礼は、この教えを実際の体験へと変えます。
一日目のアーヴァーハナでは、女性たちが身を清め、床に足跡を描いて女神を迎え、御神体は像や土器、植物など多様な形で降臨を表します。
二日目のプージャーでは、十六種類の野菜料理を捧げ、家族や隣人と分かち合うことで自然や神の恵みを共同体に広げます。
三日目のヴィサルジャナでは、御神体を水辺に還し、女神の力が宇宙へ溶け込み自然を活性化すると信じられています。
この祭礼にはヒンドゥー教の核心が反映されています。
シャクティ信仰では女性原理が慈愛と破壊の両面を持ち、ガウリー女神とジェーシュター女神を共に祀ることは、その二面性を受け入れ、創造と破壊の循環を暮らしに取り入れる実践といえます。
またガウリー女神は「マヘール」、つまり里帰りする娘と捉えられ、女性たちは女神を我が子のようにもてなします。
これにより儀礼は形式を超え、愛情に根ざした親密な信仰となり、神と人との距離を縮めていきます。
ジェーシュタ・ガウリー・アーヴァーハナは、吉も凶も、光も影も区別せずに受け入れ、そこに調和を見いだそうとする祭礼です。
不運を象徴するジェーシュター女神を祀ることで、人は試練を恐れず、それを成長や繁栄へとつながる転機として受け止められるようになります。
また、女神を迎え、もてなし、そして送り出す一連の流れは、生と死、顕現と還元といった宇宙の循環を表しています。
そこには「生かされていることへの感謝」と「相反するものを調和させる智慧」という深い教えが込められています。