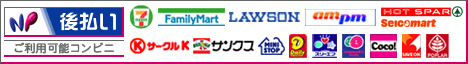シータラー・サータム
シータラー・サータムについて

インド西部グジャラート州では、モンスーンの雨が大地を潤す時期に、「シータラー・サータム」と呼ばれるシータラー女神を讃える祭りが行われます。
この祭りは、ヒンドゥー暦のバードラパダ月(8月〜9月)、クリシュナ・パクシャ(満月から新月へ向かう半月)の7日目(サータム)に斎行されます。
高温多湿なこの時期は疫病の流行しやすい季節であり、人々は病を鎮める神としてのシータラー女神に深く祈りを捧げてきました。
シータラーとは「冷たさ」を意味し、熱病や天然痘を司る女神です。
シータラー女神はロバにまたがり、手にほうき、箕、水がめ、薬草を携える姿で描かれます。
これらは、浄化、識別、癒し、救済といった女神の霊的な力を象徴しています。
ロバもまた謙虚さと忍耐、そして病を運ぶ両義的な存在として、シータラー女神の二面性――怒りと慈悲――を示しています。
祭りは前日の「ラーンダナ・チャタ」から始まります。
この日、女性たちは翌日の食事を準備し、かまどの火を消して女神への礼拝を行います。
当日の「シータラー・サータム」には火を使わず、前日に調理した料理のみを口にし、女神の本質である「冷たさ」を生活に取り入れます。
これは霊的に「熱」(病や災厄)を遠ざけ、無病息災を願う行為とされています。
神話では、疫病をまき散らす熱の悪魔ジュヴァラースラに苦しむ人々を救うため、パールヴァティー女神がシータラー女神として顕現し、悪を打ち倒します。
その後、悪魔はロバとなり、シータラー女神の乗り物として従うようになったと伝えられます。
これは病そのものがシータラー女神の支配下にあることを象徴しています。
シータラー女神の信仰は北インドにも広がり、「バソーダー(別名:シータラー・アシュタミー)」として、季節の変わり目である春に祝われる例もあります。
しかし、グジャラートの祭りはより切実に、モンスーン下の病の脅威に応じた祈りとして根づいています。
これらの祭りに共通する「火を使わない」「冷たい食事をとる」慣習は、女神の「冷たさ」によって霊的な平安を得ようとする深い知恵の表れです。
この祭りは、病を不浄として清め、自然の脅威と共に生きる知恵として、神話と日常を結ぶ「生きた信仰」として現代にも受け継がれています。
冷と熱、慈悲と畏怖の間に宿る霊性が、グジャラートの人々の暮らしの中に息づいています。