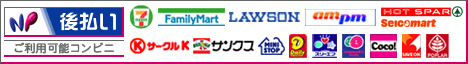ラーンダナ・チャタ
ラーンダナ・チャタについて

インド西部グジャラート州に古くから伝わる「ラーンダナ・チャタ」と「シータラー・サータム」は、家庭の安寧と健康を願う二日間の霊的祭礼です。
病や自然の脅威に対する人々の祈りと智恵が結晶した、静かで深い祈りに満ちた伝統行事として受け継がれています。
この祭りは、バードラパダ月(8月〜9月)のクリシュナ・パクシャ(満月から新月への半月)の6日目と7日目に行われます。
インドではこの時期、モンスーンの恵みによって大地が潤う一方で、湿度の高さから病が蔓延しやすく、かつては天然痘や麻疹といった致命的な疫病が流行する季節でもありました。
こうした背景の中で、人々は熱病を「冷ます」力をもつと信じられるシータラー女神に信仰を寄せ、家庭内に女神を迎え入れることで災厄を鎮め、特に子どもたちの健康を守ることを願います。
女神の御名「シータラー」は「冷たさ」を意味し、熱を伴う病を癒す存在とされます。
初日であるラーンダナ・チャタは「火」の日です。
家の女性たちは清められた身体で一日中料理に勤しみ、翌日のための冷めても食べられる伝統料理を準備します。
代表的な料理には保存性に優れたテープラーやドークラー、そして女神への供物として甘いクーレルなどがあります。
料理は母から娘へと伝承され、家族の絆を深める機会ともなっています。
日没後、かまどの火を丁寧に鎮め、牛糞と米粉で清めの儀式が行われます。
このかまどは、女神を迎える祭壇へと姿を変え、灯明や果物が供えられます。
「冷たさ」を本質とするシータラー女神を招くために、熱の象徴である火を断つこの行為には、火の神アグニへの感謝と自然の秩序への敬意が込められています。
二日目のシータラー・サータムでは、火を使わず、前日に用意された冷たい料理を食べ、静かに女神の加護を願います。
この禁火の由来には、火種を隠した嫁の過ちとその悔い改めを描いた民話があり、シータラー女神が持つ慈悲と赦しの側面を伝えています。
これらの儀礼には、日常の喧騒から離れて自然と霊性に向き合うという意味があります。
冷たい食事を摂る実践も、欲望を抑え、免疫力を高めるという智慧と結びついています。
そして、中心となるのは家庭を守る女性たちの存在であり、日々の営みの中に神聖さを見出すこの祭りは、祈りと生活が一体化した霊的実践です。
ラーンダナ・チャタとシータラー・サータムは、華やかではないものの、家庭という身近な空間に神を迎え入れる力強い信仰の表れです。
それは、病への恐れを超えて日常に神を招き入れ、古の神話が今なお人々の暮らしの中に息づいていることを示す、静かで美しい祭礼として生き続けています。