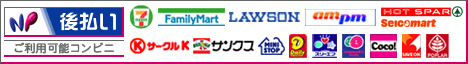ラーマーヌジャ・ジャヤンティー
ラーマーヌジャ・ジャヤンティーについて

ラーマーヌジャ・ジャヤンティーは、ヒンドゥー教ヴィシュヌ派の偉大な思想家ラーマーヌジャの誕生を祝う祭礼です。
この吉日は、特に南インドやヴィシュヌ派の伝統を受け継ぐ地域で深い敬意とともに迎えられ、ラーマーヌジャが遺した霊的な光が今も多くの人に届いていることを思い起こす機会となっています。
ラーマーヌジャ・ジャヤンティーは、タミル暦とヒンドゥー暦に基づき決まります。
基準となるのは、誕生時の月の星ティルヴァティライ(サンスクリット名:アールドラー)です。
この星がタミル暦のチッティライ月(4月〜5月)に巡る日に祝われます。
一方、他の暦を用いる場合では、ヴァイシャーカ月(4月〜5月)のシュクラ・パクシャ(新月から満月へ向かう半月)のパンチャミー(5日目)となる場合もあります。
ラーマーヌジャは、神への愛を中心に据えた思想「ヴィシシュタードヴァイタ(制限不二一元論)」を説いた人物として広く知られています。
その生涯は、真理を探求する知性と、神を想う熱い思いに満ちていました。
タミルナードゥ州の村に生まれたラーマーヌジャは、幼い頃から宗教への関心が深く、学問の中心地カーンチープラムでヴェーダの教えに親しみました。
師との意見の違いから独自の道を歩み始めたラーマーヌジャは、親しみ深く神と結びつく考え方を重視し、厳格な無個性の理論とは一線を画しました。
ラーマーヌジャの精神的な旅路には、多くの出会いがあったとされます。
中でも、シュリーランガムの聖職者ヤームナーチャーリヤや、厳しい修行の末にマントラを授けたゴーシュティプールナとの関わりは大きな意味を持ちました。
やがて出家し、シュリーランガムに拠点を移したラーマーヌジャは、思想の指導だけでなく、寺院の組織運営にも力を注ぎました。
儀式の体系化、土地や資源の管理などを通じて、実務と信仰の調和を実現させました。
とりわけ「パーンチャラートラ・アーガマ」を中心とした寺院儀礼の整備は、その後のヴィシュヌ信仰に大きな影響を与えたとされます。
ラーマーヌジャの教えは理論だけでなく行動にも裏打ちされています。
迫害を受けた際には命を守るため南方へ逃れましたが、亡命先のメールコーテーでは新たな拠点を築き、そこでも多くの人々を導きました。
多様な思想背景をもつ人々とも交わり、対話を通じて共感を育んだと伝えられています。
人が生まれてきた目的は、神と一体となることにあるとされます。
そして、そのための道としてラーマーヌジャは二つの方法を示しました。
ひとつは神への愛に根ざしたバクティ・ヨーガであり、もうひとつは全身全霊をゆだねるプラパッティです。
前者は修行と学びを重ねながら深めていく道であり、後者はすべてを神に委ねる姿勢に貫かれています。
このような教えと生き方を讃えるラーマーヌジャ・ジャヤンティーは、単なる祝祭日を超えた意味を持ちます。
ラーマーヌジャが示した献身の道は、人種や身分を越えた平等な価値を大切にし、人間の内に宿る光を見つめる視点を育みます。
この日は、生誕地シュリーペールンブドゥルや活動の中心地シュリーランガム、亡命時代を過ごしたメールコーテーなどで、盛大に祝われます。
寺院では神像への沐浴儀式、奉納の祈り、聖典の朗読、講話などが終日行われます。
町中を練り歩く神輿の行列は、多くの人々の心を一つにする機会となっています。
ラーマーヌジャ・ジャヤンティーは、過去を懐かしむ日ではなく、今を見つめ直す日でもあります。
ラーマーヌジャが築いた信仰と思想の架け橋は、現代に生きる人々にも、希望と安らぎ、そして内なる神性を思い起こさせてくれるでしょう。