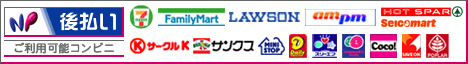カーラーダーイヤナ・ナウンブー
カーラーダーイヤナ・ナウンブーについて

カーラーダーイヤナ・ナウンブーは、サーヴィトリー・ヴラタムとも呼ばれる南インドの重要な祭事です。
主にタミル・ナードゥ州で既婚女性によって祝われ、愛の力と妻の献身、そして運命への勝利を象徴しています。
この祭事は南インドの各州だけでなく、タミル系住民が多い海外の国々でも盛大に行われています。
この祭事はタミル暦のパングニ月(3月〜4月)の初日に行われ、太陽が水瓶座から魚座へ移行する時にあたります。
これは新たな始まりと善の悪に対する勝利を象徴する吉兆な時とされています。
カーラーダーイヤナ・ナウンブーの中心となるのは、サーヴィトリーとサティヤヴァーンの心を打つ神話です。
マハーバーラタに登場するこの神話は、比類なき愛と献身の象徴として語り継がれています。
アシュヴァパティ王の娘サーヴィトリーは、その美しさ、知恵、敬虔さで知られ、森での亡命生活を送っていた王子サティヤヴァーンを夫として選びました。
賢者ナーラダから結婚後一年以内にサティヤヴァーンが死ぬ運命にあると警告されたにもかかわらず、サーヴィトリーは彼との結婚を選び、真の愛の意味を世に示すことになります。
結婚後、予言通りにサティヤヴァーンの命が尽きる日が訪れました。
薪を集めるために森へ入った夫に付き添ったサーヴィトリーは、突然倒れたサティヤヴァーンの魂を死の神ヤマが連れ去ろうとするのを目撃します。
夫の運命を受け入れられないサーヴィトリーは、ヤマ神の後を追いました。
最初はサーヴィトリーの嘆願を退けていたヤマ神も、次第に彼女の揺るぎない献身と深いダルマ(正義の行い)の理解に心を動かされます。
ついに、ヤマ神はサーヴィトリーに、夫の命以外なら何でも願いを叶えると申し出ます。
サーヴィトリーは巧みにこの申し出を活用し、最初に義父の視力と王国の回復を願い、次に父親に百人の息子を、最後に自分とサティヤヴァーンに百人の息子を願いました。
三つ目の願いによってヤマ神は窮地に立たされます。
サーヴィトリーに子どもを与えるためには、サティヤヴァーンを生き返らせる必要があったからです。
サーヴィトリーの献身と機知を認めたヤマ神は譲歩し、サティヤヴァーンを生き返らせました。
このサーヴィトリーの勝利の日が、カーラーダーイヤナ・ナウンブーの由来とされています。
この祭事は「パティヴラタ・ダルマ」という、妻の献身と忠誠の理想を象徴しています。
パティヴラタ・ダルマとは、妻が夫に全身全霊を捧げ、夫の幸福を追求し、その精神的・現世的な歩みを支える役割を重んじる考え方です。
サーヴィトリーの行動は、死をも恐れず夫への愛を貫いた女性の内なる強さを表しています。
また、この神話は様々な解釈が可能です。
寓話的には、サティヤヴァーンは死すべき自己、サーヴィトリーは不滅の魂を象徴し、心理学的には人間の精神の内なる葛藤と自己変容のプロセスを表しています。
宇宙論的には、サーヴィトリーが創造と維持の力を、ヤマ神が破壊と変化の力を象徴し、これらの相反する力が宇宙の均衡を保つために不可欠であることを教えています。
カーラーダーイヤナ・ナウンブーは、家族の幸福と調和を祈願する深い精神性を持ち、現代においても多くの家庭で大切に守られています。
既婚女性たちは「サウバーギャ」(吉兆や幸運)と「サウマーンガリャ」(長く実りある結婚生活)を願い、心を込めた祈りと共に伝統的な作法を守り、家庭の平和と繁栄を神々に願い求めます。
この祭事が長年にわたり人々を惹きつけるのは、愛と献身の力、そして人間の精神が試練を乗り越える美しい物語があるからです。
「愛は死をも超える」という普遍的なテーマは、どんな困難にも立ち向かう人間の精神の強さを思い起こさせ、私たちの人生に希望と勇気を与え続けています。