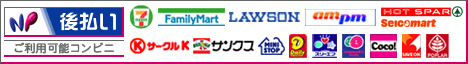パールグナ・アシュターフニカー
パールグナ・アシュターフニカーについて

パールグナ・アシュターフニカーは、ジャイナ教における重要な八日間の祭儀として知られます。
「アシュターフニカー」という言葉は、「アシュタ(八)」と「アーフニカ(毎日)」に由来し、八日間にわたる祭儀を意味します。
アシュターフニカーは年に3回あり、それぞれパールグナ月(2月〜3月)、アーシャーダ月(6月〜7月)、カールッティカ月(10月〜11月)において、シュクラ・パクシャ(新月から満月へ向かう半月)の8日目から満月にかけて行われます。
この祭儀の特徴は、八日間にわたる毎日の崇拝と寺院の参拝、断食と節制、瞑想と経典学習を通じて、霊的な修行を深め、カルマの浄化と解脱への道を追求することです。
パールグナ月は冬から春への移行期であり、自然の再生と復活の時期と重なることで、浄化と内省、霊的成長の象徴的意味を持ちます。
祭儀は、ナンディーシュヴァラ・ドヴィーパの伝説と結びついています。
ジャイナ教の宇宙論では、世界は上界・中界・下界に分かれており、ナンディーシュヴァラ・ドヴィーパは中界の第八の島とされます。
この島には52の寺院があり、天界の存在のみが参拝できるとされています。
祭儀の期間中、ジャイナ教徒はこの天界の崇拝を地上で象徴的に再現します。
また、解脱を達成した敬虔な修行者ピンガラ・クマーラを追想する機会としても重要です。
その生涯は、世俗的執着からの離脱、内なる平安の育成、完全な解放と悟りへの到達という段階的な解脱の過程を示しています。
これは、日常生活の中で霊的な実践を続けることの重要性を教えています。
祭儀は、ジャイナ教の五つの主要原則と密接に結びついています。
- アヒンサー(非暴力):あらゆる生命への不害
- アステーヤ(不盗):与えられていないものを取らない
- サティヤ(真実):真実を語り行動する
- アパリグラハ(無所有):物質的欲望の抑制
- ブラフマチャリヤ(純潔):エネルギーの賢明な使用と自制心の育成
これらの原則は、ジャイナ教徒の思考、言葉、行動を導く指針となり、パールグナ・アシュターフニカーはこれらの原則について深く考え、自らの決意を新たにする機会を与えます。
パールグナ・アシュターフニカーは単なる儀式の集まりを超えて、霊的な成長と浄化、そして究極的な解脱への道筋を示す霊的な旅路となっています。
古代の叡智と現代の実践が調和する場として、ジャイナ教の伝統の中で重要な位置を占めています。