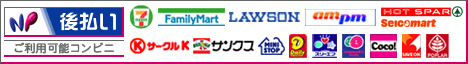ガウリー・ヴラタ
ガウリー・ヴラタについて

インド西部・グジャラート州で広く行われている「ガウリー・ヴラタ」は、ヒンドゥー教における特別な霊的修行で、未婚女性が理想の伴侶を願い、既婚女性が家庭の幸福を祈るために行う五日間の断食の誓いです。
アーシャーダ月(6月〜7月)のシュクラ・パクシャ(新月から満月へ向かう半月)のエーカーダシー(11日目)に始まり、五日後の満月まで続きます。
「ガウリー」とはパールヴァティー女神の別名で、「輝き」や「吉兆の光」を意味します。
優しさと力強さを併せ持ち、夫であるシヴァ神の厳格な性質と調和を成す存在です。
このヴラタ(誓願)は、パールヴァティー女神がシヴァ神と結ばれるまでに重ねた壮絶な修行を手本とし、自らの生活の中に霊的な規律を取り入れる試みとされています。
この修行の核となるのは、感覚の制御を目的とした食事制限です。
「モーラカト・ヴラタ」と呼ばれるこの断食では、塩・香辛料・一部の野菜を避け、果物や乳製品などに限った食事を摂ります。
それは単なる禁欲ではなく、心と身体を静め、祈りに集中するための準備とされています。
ヴラタ初日には、小麦や大麦の種が土鍋に蒔かれ、五日間育てられます。
これは豊かさと心の成長を象徴するもので、麦の芽の伸び具合は実践者自身の内的成長と重ねて受け取られます。
各日、聖なる壺に灯明や花を捧げ、女神に祈りを捧げる儀礼が行われます。
五日目の夜には、「ジャーガラナ」と呼ばれる徹夜の祈りがあり、眠らずに夜を明かすことで、パールヴァティー女神の厳しい修行に身を重ねます。
この祈りは、精神力と信仰心の集大成であり、日常の中で失われがちな集中と意志を再び手にする機会でもあります。
六日目の朝、女性たちは清らかな衣に身を包み、育てた麦を聖なる川に捧げることで儀式は締めくくられます。
こうして断食は終わり、再び日常生活に戻っていきますが、女性たちは何か新しい視点や内面的変化を感じることも少なくありません。
このヴラタの背景には、ふたつの重要な物語が語り継がれています。
ひとつは、パールヴァティー女神が長い年月にわたり厳しい修行を行い、最終的にシヴァ神に認められる物語です。
パールヴァティー女神は王女の身分を捨て、氷水の中で瞑想し、火や雨に耐え、食すら断つことで自らの霊性を高めていきます。
その力は神々すら驚かせ、ついにシヴァ神を動かすまでに至りました。
もうひとつの物語は、子を望む敬虔なバラモン夫婦の話です。
ある日、夫が毒蛇に噛まれ命を落としたように見えた際、妻が真心からパールヴァティー女神に祈ることで夫は蘇り、やがて子を授かるに至ります。
この出来事をきっかけに夫婦はガウリー・ヴラタに取り組み、多くの人々がその教えに従うようになりました。
この五日間の実践を通じて育まれるのは、単なる信仰ではなく、「意志」と「行動」と「知恵」の調和です。
自ら立てた誓いに従って日々を送り、祈りと努力を重ねることで、人生そのものが霊的な道となっていきます。
とりわけ若い女性たちにとって、このヴラタは家庭を築く準備でもあります。
家庭とはただの責任ではなく、内なる強さと祈りによって支えられる場であり、妻とは静かに従う存在ではなく、家庭に光をもたらす霊的な柱である――そんな教えが、この伝統には込められています。
ガウリー・ヴラタは、古来からの誓願の形にとどまらず、時代を超えて今を生きる私たちに、内なる力と清らかな意志の尊さを教えてくれる大切な行となっています。